地盤改良工事を大幅に削減する正確な地盤調査 表面波探査法による調査
宮崎・鹿児島の地盤調査の事なら
|
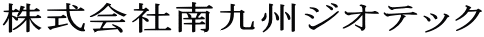 |
|
|
|
| |
| 01 報告書の構成と読み方の基本 |
|
「表面波探査法の報告書はよく分からない・・・」という方のために、このホームページでは地盤調査報告書を分りやすく解説いたしました。
|
| 基本の3つをおぼえましょう
グラフ読み方の基本からご説明いたします。この3つをおぼえてしまえば、あとは簡単です。
【基本その1】グラフの基礎 2つの速度値
表面波探査は表面波の伝わる“速さ”を測っています。周波数を細かく変化させて、深さ方向につぶさに情報を集めていきます。
測定時に得られるのは“平均速度”の値です。地表面から計算している深さまでの平均の速度を測っています。
測定時に得られた“平均速度”の値から解析作業を行い“区間速度”を計算します。
解析作業の中で、まずどこからどの深さまで一つの区間(地層をイメージして下さい。)であるということを明らかにします。
次に、その区間がどのくらい硬いのか、あるいは軟らかいのかを“区間速度”の値で明らかにします。
- 平均速度…地表面からその深度までの平均な地盤の硬軟を表すの速度値
- 区間速度…その深度の地盤の硬軟を表わす速度値
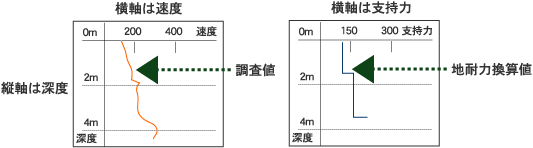
【基本その2】区間速度から支持力へ
区間速度は、地層の境界深さを明らかにし、その各層がどのくらいの硬さ軟らかさであるということを示しています。
この区間速度から地盤の支持力(地盤の許容応力度)を計算します。つまり、NO.1のポイントでは何m、何m・・・に地層の境界があり、各層の支持力は、何kN/?、何kN/?です、という地盤の情報が明らかになります。
【基本その3】単位は3つおぼえて下さい
| Vr |
速度 |
軟らかい物はゆっくりと波が伝わります。硬い物は波が早く伝わります。波の伝わる速度は、物の硬い軟らかいの判断基準になります。波の伝わる早さは支持力に換算することが出来ます。こうして、その地盤がどのくらいの重さを支えることが出来るのかを見極めます。 |
| D |
深度 |
探査深度です。 |
| f |
周波数 |
波は振動しながら進んでいきます。周波数は1秒間に何回振動するという値です。波動は、波の速度と周波数には密接な関係があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 02 安心と保証の証明 |
|
表面波探査は、公的機関から認定をうけています。
証明書と認定証。そして基礎考察
ここではお客様へお送りする報告書の最初に添付されている表面波探査法の技術審査認定と、地盤を調査する調査員、そしてお客様へまず第一報をお送りする「基礎考察書」についてご説明します。
技術と調査員についての証明
表面波探査法の「技術審査証明書」と「表面波探査員認定証」の説明
|
 |
- 技術審査証明書
- 財団法人先端建設技術センターより技術審査証明を取得しています。
これは地盤の調査手法では唯一、表面波探査だけです。
この技術審査の中で、ボーリング試験などとの比較を行い、確かな技術であると証明されました。
|
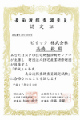 |
- 表面波探査調査員
- 1年に一度、表面波探査に関する試験を行っています。
認定書はこの試験で然るべき水準に達した方のみ発行しています。
その他、年に数回の技術講習会を開き、表面波探査の技術レベルを向上させています。
|
|
基礎考察書は調査結果の速報
表面波探査の結果は、あまりお待たせしない段階で調査結果速報をお出ししています。調査結果速報と基礎考察書は同じ内容になります。
|
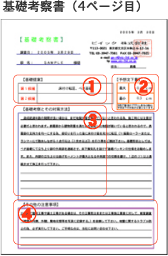 |
?基礎提案
表面波探査の結果、必要である、あるいは適当であると考えられる、各種工事、基礎形状について、提案させていただいております。表面波探査の結果です。
?予想沈下量
地盤の支持力だけではなく、沈下量を予測し、この部分からも基礎提案を行っています。
?基礎考察と対策方法
調査地の地盤について、調査結果についてのやさしい説明をさせていただいております。
また、調査結果から基礎提案を行い、細かい説明をしています。
?その他の注意事項
工務店様、エンドユーザー様にたいして、住宅完成後も含めて気をつけて頂きたい事などが書かれています。
|
|
|
|
調査概要と調査方法説明
調査の概要や表面波探査法の原理を理解いただくためのページです。しかし、原理や数値の読み方などは簡略化された解説ですので、ご不明点等は本ホームページをご参照下さい。
|
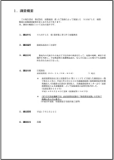 |
■調査概要(5ページ目)
調査地住所、発注者様、およびエンドユーザー様を意識して、調査を行っています。調査段階でこれらの情報は、データに付記しますので、データの取り違いや調査場所を間違うといった問題が生じることがありません。
さらに、国土交通省告示第1113号の調査手法として表面波探査が合致していることや、財団法人住宅保証機構においても調査手法として認められている旨を明記しています。さらに、調査を行った日付、調査を行った担当者名をあげています。 |
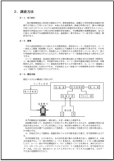 |
■調査方法(6ページ目)
表面波探査の基本的な説明です
|
|
|
| 03 調査結果 |
| 皆様は地盤調査についてご存知のことと思いますが、今一度そのリスクや調査方法について一緒に学んでみませんか。よくご存知の単位でもってご説明いたします。 |
調査結果表の読み方
調査結果は、解析結果から判断した地盤特性、およびこれらを考慮した基礎形状の提案をしています。
簡単に読み方を説明します。
地盤支持力を理解しましょう
|
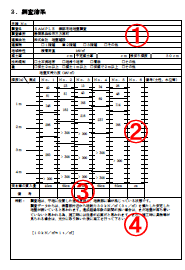 |
?調査概要
工事名、調査地住所など
?調査結果グラフ
地盤の支持力、各測点における深度方向の支持力分布を表しています。
?突棒貫入量
表面波探査を行うと同時に、長さが110cm、太さが2cmの鉄の棒を地面に刺します。ガラの存在について確認します。
?特記
調査地の特徴や調査の結果について。また、調査の結果何らかの地盤対策が必要であるか否かや、基礎形状について調査およびデータ解析者の考察が入ります。
各測点において、地盤の硬さがどのくらいの深さからどうなっているということが、突き棒の結果とともにまとめられています。次の頁の周辺状況表に示した調査地の状況や概略的な地形情報などから、住宅をどのようにたてるべきなのかを判断します。
|
|
|
|
- コツをつかんでしまえば読むのはカンタン
- 総合判断はいろいろな要素を含めて行います。表面波探査のデータだけではなく、調査地や周辺地形がどうなっているなどの情報も加味します。
|
調査概要と調査方法説明
|
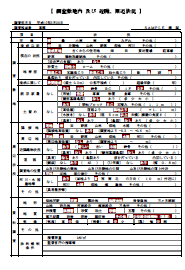 |
- ●調査地周辺状況表
- 調査地の造成状況や地域性といったものを考慮することにより、より精度の高い判断をすることにつながります。
- 調査敷地
- 調査地が昔どのような土地であったのか、また現況がどのように造成されているのか、調査する段階でも確認しています。粘性地盤なのか砂質地盤なのか。また建物取り壊した時のガラなどが含まれているかどうかなどを、目視や機材を用いて確認します。
また、地盤が自然地盤なのか、それとも人工地盤なのか、人工地盤であればどのように造成されたのか等、地盤の強度に影響する事柄(擁壁の有無及び規模など)について調査し、周辺状況表へ反映します。 - 周辺状況
- 調査地の近隣は地盤状況が似通っていることが多いです。隣地、あるいは周辺地がどのような状況であるのか(田畑、河川、住宅地など)を確認します。
地表近くを上手に造成していたとしても、その地域の地盤が持つ、性質まで変えるのは難しい場合が多いです。既に構造物(家屋、道路など)があり、それらが何らかの変状を示している場合、それらのことも考慮にいれ解析および総合判断をします。 - 資料調査
- 現地では確認できない、地域の概略的な地質、地形については、調査前段階で可能な限り資料調査も行います。
|
|
|
|
| 04 支持力別推定断面図の読み方 |
|
皆様は地盤調査についてご存知のことと思いますが、今一度そのリスクや調査方法について一緒に学んでみませんか。調査地の地盤の中を立体的に考えます。
支持力別推定断面図は地盤の強さを簡易化したもの
|
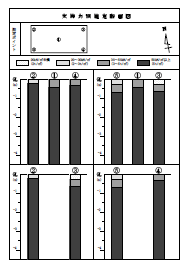 |
グラフを読むにはちょっとした想像力が。
表面波探査は5箇所で行っています。報告書では4方向にデータを並べた断面図を表示しています。ここから、少しだけ想像力を働かせてみて下さい。立体的に地盤状況を想像すると、地層の傾斜がどのようになっているか分かりますでしょうか。
|
|
|
|
|
支持力別推定断面図です。
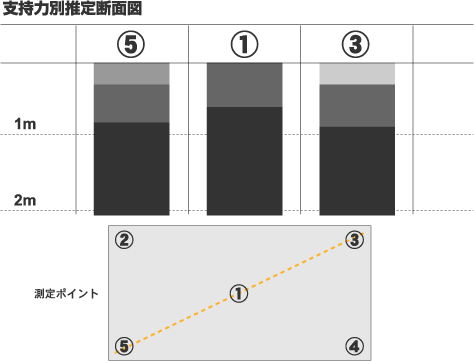
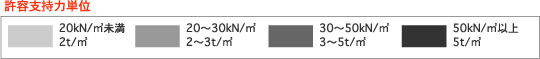
上の図は報告書の中の1頁です(報告書サンプル*頁目)。
調査地にて5箇所(1〜5)の測定を行い、解析結果を3点(1,3,5)を並べたものです。5→1→3の順番で表面波速度の高いしっかりとした地盤が深くなっている(傾斜している)のがわかります。
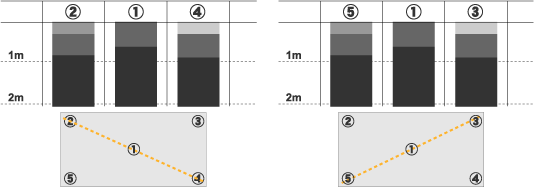
同様に、対角となる3点(1、2、4)の解析結果を並べます。2→1→4の方向に地盤が傾斜しているのがわかります。
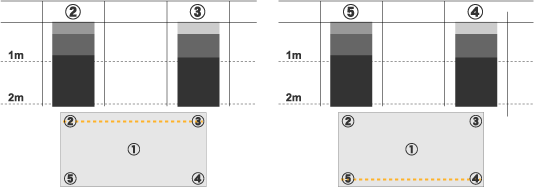
さらに、2点(2、3および4、5)でもデータを並べて地盤の傾斜の状態を確認します。この4方向でデータを並べることで、地盤内部の傾斜状況を立体的に捉えることが出来ます。

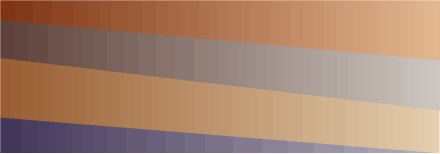
調査配置図
調査配置図は、調査位置を表記する役割がありますが、それだけではありません。表面波探査を行うと同時に、敷地の状況について写真やメモをとり、解析の1要素としています。これらの情報については、調査地周辺状況表や、調査配置図へ反映します。
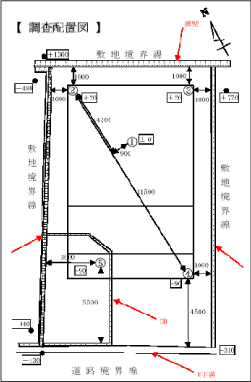
- 調査配置図に反映している項目
- □敷地形状
- □建物配置位置
- □周辺構造物(擁壁、水路、ブロック塀等)
- □各測定位置
- □近隣地との高低差
- □他
- コツをつかんでしまえば読むのはカンタン
- このように、立体的に地盤状況を判断することで、工事内容や基礎提案の精度を高め、安全で尚かつ過剰な工事などを減らすコンサルティングさせていただいております。
|
| 05 各種グラフの読み方 |
|
皆様は地盤調査についてご存知のことと思いますが、今一度そのリスクや調査方法について一緒に学んでみませんか。速度から支持力へ換算します。
曲線と階段はその深度の地盤の硬さを表わします
区間速度グラフの読み方 単位が分かれば簡単です
区間速度グラフと許容支持力換算グラフの読み方についてご説明します。まずはこの3つの単位をおぼえて下さい。
D(m)=深度
Vr(m/s)=速度
qa(kN/?)=支持力
下の図(区間速度グラフ)で一度区間速度になった数字を右の図(許容支持力換算グラフ)に換算しています。
|
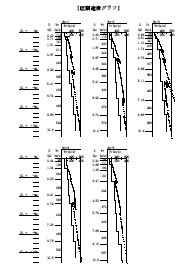 |
区間速度グラフは階段状になっています。縦方向が深さ、横方向が速度になります。また、点線の曲線は、測定データ(平均速度値)になります。測定データを解析することで、区間速度グラフ(層ごとの速度値)を明らかにします。 |
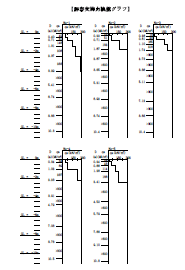 |
区間速度の値を、換算することで各層の支持力(許容応力度)を算定します。このとき国土交通省告示1113号に揚げられている支持力換算式に則って算定しています。 |
|
|
区間速度グラフ
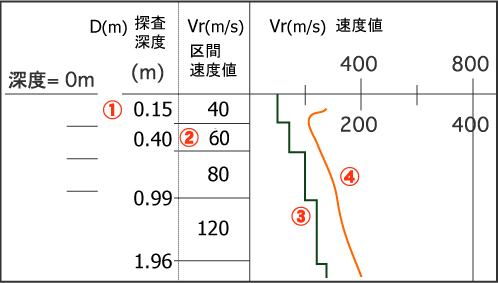
許容支持力換算グラフ
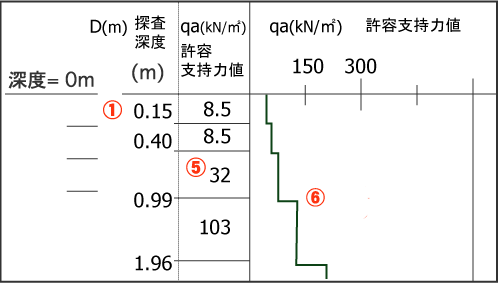
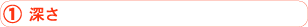
測定データを解析することで得られた、地層境界の深さです。
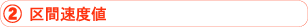
測定データを解析し、判別した各層の持つ速度値です。地盤の硬さの判断材料となります。
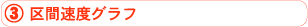
区間速度値を階段状のグラフで表しています。
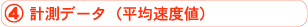
測定データです。1点1点が、地表面からその深度までの平均速度を表しています。
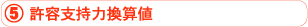
区間速度値を換算した、地盤の許容応力度の値です。
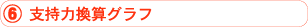
区間速度の値を、換算することで各層の支持力(許容応力度)を算定します。このとき国土交通省告示1113号にあげられている支持力換算式に則って算定しています。
|
|
| 06 沈下量について |
|
皆様は地盤調査についてご存知のことと思いますが、今一度そのリスクや調査方法について一緒に学んでみませんか。
地耐力は、地盤の支持力と沈下特性の両方のことを指します。
【基本その1】沈下量予測とは?
軟らかく、ぬかるんでいる地面を歩くと、足がずぶずぶと沈んでいきます。硬い地面であれば、足跡すらつかないこともあります。沈下量予測とは、地盤の特性を見極め、仮想で住宅の程の荷重を地盤にかけ、住宅は沈下するのか、最大どのくらい沈下するのかを算定します。
【基本その2】二つの沈下量
地盤に鉛直方向に力を加えると、2種類の変化が起きます。
 - 即時沈下は、力を加えた直後の地盤の変形です。
 - これに対して、圧密沈下は、最初は加わった力を受け止めて均衡するのですが、地盤の間隙比の変化や排水作用によりゆっくりと沈下していく地盤の変形を指します。
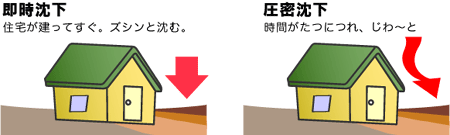
即時沈下量および圧密沈下量ともに、表面波探査の結果から計算しているのですが、現地の状況によっては測定結果だけでは、長期の圧密沈下を予測するのに十分ではない場合もあります。
造成中あるいは、掘削して間もない人工地盤、旧建物を取り壊した際や、ガラなどの異物を多量に混入している不適合材料(産廃など)を盛土材料に用いている場合など。表面波探査の結果とこれらの条件をもとに、即時沈下量と圧密沈下量を算定します。この2つの値を足したものが、予測される沈下量になります。
【基本その3】報告書の内容
各速度計算表
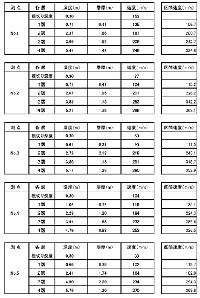 5地点での測定の結果、どの位の深さに層境界があり、また各々の1〜4層がどのくらいの硬さ(速度値)をもっているのかを示しています。表面波探査の結果です。 5地点での測定の結果、どの位の深さに層境界があり、また各々の1〜4層がどのくらいの硬さ(速度値)をもっているのかを示しています。表面波探査の結果です。
沈下量計算
●諸条件の入力
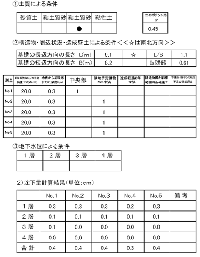 沈下量計算を行う上で、土質、地下水位、建物の形状などの条件を示しています。 沈下量計算を行う上で、土質、地下水位、建物の形状などの条件を示しています。
計算根拠
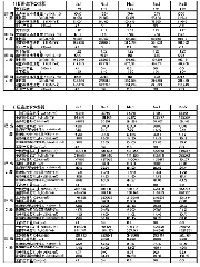 さきにふれましたように、沈下とは即時沈下と圧密沈下との合計となります。 さきにふれましたように、沈下とは即時沈下と圧密沈下との合計となります。
計算過程の中で得られる主要な数値および沈下量を示しています。
区間速度グラフ
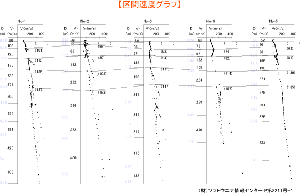 各層の伏在深度がどのくらいかを示しています。同時に各々の層がどのくらいの速度値をもっているのかを表示しています。 各層の伏在深度がどのくらいかを示しています。同時に各々の層がどのくらいの速度値をもっているのかを表示しています。
支持力換算グラフ
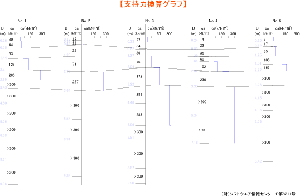 各層の伏在状況と各々の持つ支持力値を得ています。 各層の伏在状況と各々の持つ支持力値を得ています。
|
- コツをつかんでしまえば読むのはカンタン
- 国土交通省告示第1113号において、地盤の支持力(地盤の許容応力度)を求めなければならないとされています。また、これと平行して、建物荷重による沈下その他の地盤変形を考慮し、建物に有害な損傷、変形が生じないことを確かめなければならない、ともされています。
支持力と沈下量のどちらも確認しなければならないということになります。
|
|
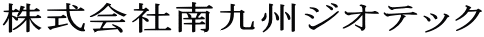
宮崎県都城市早鈴町1745番地2
電話(0986)36-4028
ファックス(0986)36-4027 |